この記事では、ひとり親が受けられる控除についてまとめたよ。
受けられる手当もいろいろ紹介しているから、対象になる手当があるか確認してみて!
控除や手当って活用したいけど、申請や条件を確認するのが大変じゃない?
 かっぴ
かっぴ自分から情報を取りに行かないと、誰も教えてくれないんだよね
そこで今回は、ひとり親が受けられる控除について、分かりやすく解説するよ。
受けられる手当についても、どんなものがあるか書いていくね◎
お金のことどうしたらいいかわからない!って人には、ほけんのぜんぶさんがおすすめ♪



保険のことはもちろん、お金のことはなんでも相談できちゃう
お金のスペシャリストへの相談はこちらから!
ひとり親が受けられる控除
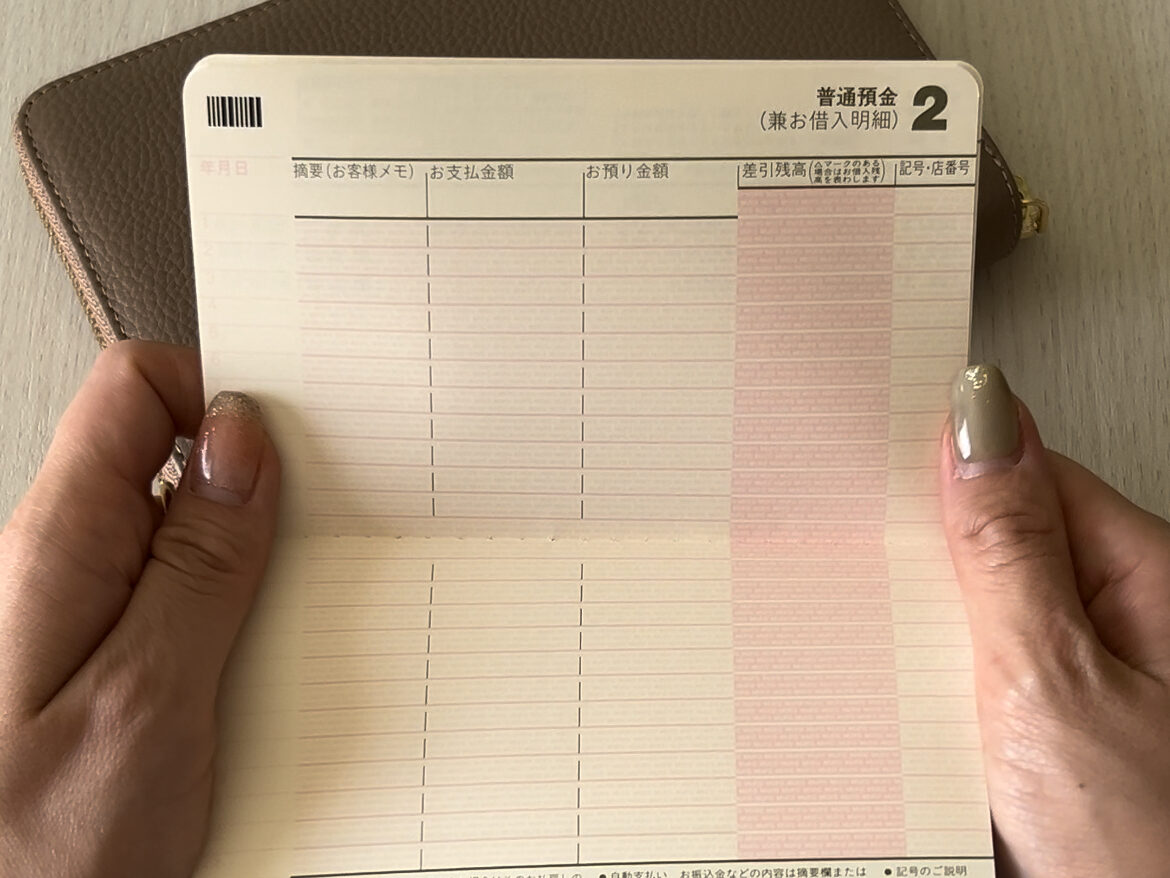
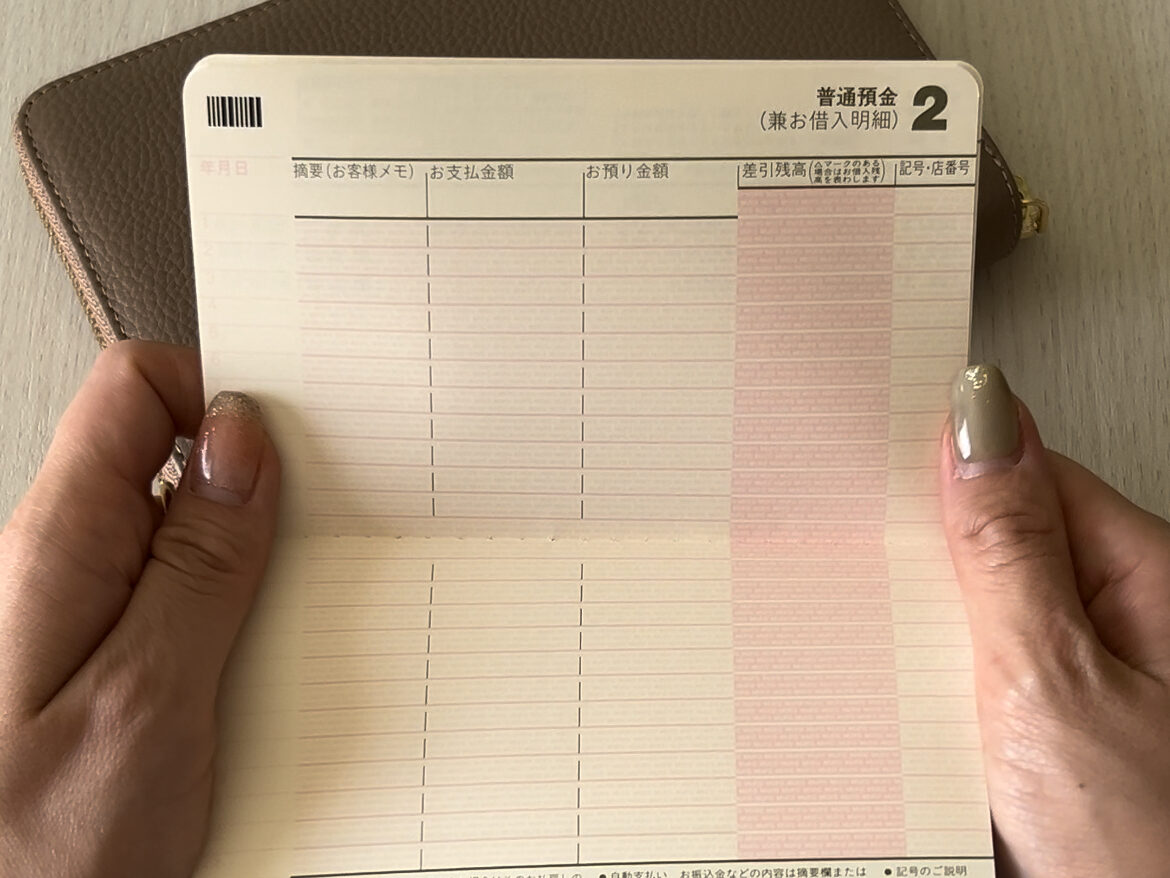
今回は、ひとり親が受けられる控除を3つ紹介するよ♪
それぞれ対象者の要件に違いがあるから、自分が対象になる控除を確認してみてね!
ひとり親控除
ひとり親控除は、シンママやシンパパなど、1人で子どもを養育する親が受けられる所得控除の制度。



この控除を活用することで、税負担を軽減できるよ!
控除額と適用対象
ひとり親控除の控除額は次のとおり。
所得税:一律35万円
住民税:一律30万円
控除を受けられるのは、次の条件を満たしている場合だよ。
- 婚姻をしていない、または配偶者の生死が不明
- 事実婚状態にない
- 家計を共有している子どもがいる(子どもの所得が48万円以下、かつほかの人の扶養親族でない)
- 申告者の合計所得金額が500万円以下



条件を満たしていれば、未婚のシンママさんもOK
控除を受けるための手続き
ひとり親控除を適用するには、年末調整または確定申告が必要だよ。



該当する人は手続きしてね!
年末調整:勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「ひとり親」にチェックを入れる
確定申告:個人事業主やフリーランスの場合、「確定申告書」の所定欄に控除額を記入。
控除が反映されるまで、住民税も含めて申告漏れがないよう注意してね
注意するべきポイント
離婚や死別が年末に発生した場合でも、12月31日時点で要件を満たしていればOK!
また、養育費を受け取っている場合、ひとり親控除が受けられない場合もあるよ。



元配偶者の、扶養親族とみなされる可能性があるんだよね
寡婦控除
寡婦控除は、離婚や死別を経験した女性が一定の要件を満たした場合に受けられる所得控除。
1人で家庭を支える女性に対する、税制優遇措置だよ。



以前は男性に対する寡夫控除もあったけど、今は廃止されているみたい
寡婦控除はひとり親控除と似ているけど、適用対象や条件が違うから紹介していくね!
控除額と適用対象
寡婦控除の控除額は次のとおり。
所得税:27万円
住民税:26万円



控除額はひとり親控除より小さいね
寡夫控除を受けられるのは、次の条件を満たす人だよ。
- 離婚後または夫と死別後に再婚していない、もしくは配偶者の生死が不明
- 離婚の場合、扶養親族がいることが必要(死別の場合は不要)
- その年の合計所得金額が500万円以下



扶養親族は、子どもじゃなくて親や孫でもOK
控除を受けるための手続き
寡婦控除を適用するためには、ひとり親控除と同じように年末調整または確定申告が必要だよ。



自分が対象かどうか確認して、必要に応じて申告しよう!
ひとり親控除との併用
寡婦控除は、ひとり親控除と併用することはできないよ。
両方の要件を満たしている場合は、控除額が大きいひとり親控除が優先されるから、覚えておいてね◎
扶養控除
扶養控除は、納税者が一定の条件を満たす扶養親族を抱えている場合、所得税や住民税を軽減するための所得控除。
控除額と適用対象
扶養控除の控除額は、次のとおり。
| 扶養親族の年齢や状況 | 控除額 |
|---|---|
| 16歳以上18歳以下(一般扶養親族) | 所得税38万円 住民税33万円 |
| 19歳以上22歳以下(特定扶養親族) | 所得税63万円 住民税45万円 |
| 70歳以上(老人扶養親族・同居以外) | 所得税48万円 住民税38万円 |
| 70歳以上(同居老親等) | 所得税58万円 住民税45万円 |



扶養親族の年齢や状況によって控除額が変わるんだね
扶養控除の対象になる扶養親族は、次の条件をすべて満たしている必要があるよ。
- 申告する年の12月31日時点で16歳以上
- 合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合、年収103万円以下)
- 納税者と家計を共有している
- 配偶者以外の6親等以内の血族または3親等以内の姻族(例:親、祖父母、兄弟姉妹、孫など)
- 青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない
- 白色申告者の事業専従者でもない



扶養親族に年齢制限があるんだね
控除を受けるための手続き
対象となる扶養親族がいる場合は、忘れずに年末調整または確定申告で申請しよう◎



ひとり親控除や寡婦控除と同じ
だね
注意するべきポイント
16歳未満のこどもは扶養控除の対象外だよ。
あと、扶養親族が親や祖父母などの場合、収入状況や仕送り金額が影響することがあるから注意!
ひとり親控除との併用
扶養控除は、ひとり親控除と併用できるよ。



もちろん、それぞれの要件を満たしていることが条件
ひとり親が受けられる手当


ここからは、ひとり親が受けられる手当を紹介していくよ♪
受けられる手当は最大限活用しよう!
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するための手当。
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもを養育している親や養育者に支給されるよ!



母子手当とも言われているよね
支給額
令和6年11月1日から、児童扶養手当の支給額が次のように改定されたよ。
| 全額支給(月額) | 一部支給(月額) | |
|---|---|---|
| 第1子 | 45,500円 | 10,740~45,490円 |
| 第2子加算額 | 10,750円 | 5,380~10,740円 |
| 第3子以降加算額 | 10,750円 | 5,380~10,740円 |
一部支給の場合は、所得に応じて支給額が
決まるよ◎



第3子以降の加算額が引き上げられて、第2子と同額になったんだよね
所得制限限度額
令和6年11月から、受給者本人の所得制限限度額が次のように引き上げられたよ。
| 扶養親族等の数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 0人の場合 | 69万円未満 | 208万円未満 |
| 1人の場合 | 107万円未満 | 246万円未満 |



今回の引き上げで、手当の有無が変わった人もいるかも♪
申請手続き
児童扶養手当の受給を希望する場合は、住んでいる市区町村の窓口で申請手続きをしてね♪
申請には、戸籍謄本や所得証明書などの書類が必要になるよ。



自分が対象になるか、必要書類は窓口で確認してみて
毎年8月には現況届の提出が必要で、怠ると手当の支給が停止されることもあるから要注意!
児童手当
児童手当は、子育て世帯の生活を支援し、子どもの健やかな成長を促進するための制度。



ひとり親制度ではないけど、みんな関係あるからチェックしよう!
支給額
令和6年10月から、支給額が次のようになったよ。
| 子どもの年齢 | 支給額(月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円、第3子 以降は30,000円 |
| 3歳以上~高校生年代 | 10,000円、第3子 以降は30,000円 |



第3子以降の児童に対する支給額が、増額されたんだよね♪
所得制限
令和6年10月以降、所得制限が撤廃されたよ!
これで所得に関わらず児童手当を受給できるようになったんだよね。



これは嬉しい♪
申請手続き
児童手当の受給を希望する場合は、住んでいる市区町村の窓口に必要書類を提出してね。



オンラインでの申請が可能な自治体もあるよ♪
申請には、児童手当認定請求書や申請者の本人確認書類が必要になるよ。
申請は、児童が出生した日や転入した日の翌日から15日以内に行ってね!



受給中に住所など状況の変更があった場合は、届け出が必要だよ
市区町村によっては、毎年6月に現況届を提出する必要があるから確認してね!
ひとり親家庭医療費助成制度


ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親家庭の経済的負担を軽減するため、医療機関での自己負担額を自治体が助成する制度。
対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(障がいがある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭だよ。
助成内容や所得制限額は自治体によって違うんだよね。



詳しいことは、住んでいる自治体の窓口で確認してみて!
たとえば、東京都の窓口で負担する金額はこんな感じだよ。
| 負担割合 | 1ヶ月あたりの負担上限額 | |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯(通院) | 1割 | 18,000円 年間上限:144,000円 |
| 住民税課税世帯(入院) | 1割 | 57,600円 多数回該当:44,400円 |
| 住民税非課税世帯(通院・入院) | 自己負担なし | 自己負担なし |
申請手続きには、申請者と子どもの健康保険証などが必要だけど、これも住んでいる自治体に確認してね。



令和7年から所得限度額が引き上げられる自治体もあるから要チェック!
ひとり親家庭住宅手当
ひとり親家庭住宅手当は、ひとり親家庭が賃貸住宅の家賃負担を軽減するための助成制度。
この制度は自治体が独自に実施しているから、助成金額や対象者の条件は各自治体によって違うよ。



制度自体がない自治体もあるから、確認してみてね
支給額の例はこちら!
| 自治体 | 支給額 |
|---|---|
| 東京都世田谷区 | 月額最大40,000円減額(指定の補助事業住宅に限る) |
| 東京都武蔵野市 | 月額10,000円(家賃が10,000円以下の場合はその 金額) |
| 千葉県君津市 | 月額5,000円(家賃が10,000円を超える部分に適用) |
自治体窓口または郵送で申請してね♪



家賃支払いを証明する契約書などが必要になるので、自治体に確認しよう
そのほかの支援
ひとり親家庭の支援には、ここまで紹介してきた手当のほかにもいろいろあるよ!



代表的な支援をいくつか紹介するね
乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度
乳幼児や義務教育中の子どもの医療費のうち、自己負担分を助成する制度。
乳幼児医療費助成制度(マル乳):幼稚園児や保育園児が対象
義務教育就学児医療費助成制度
(マル子):小学1年生から中学3年生までの子どもが対象



これも自治体によって、助成の内容や対象年齢、所得制限が違うよ
特別児童扶養手当
20歳未満で、重度の精神または身体障害を持つ子どもを養育する家庭に支給される手当。
支給額はこちら!
1級(重度障害):月額55,350円
2級(中度障害):月額36,860円
参考|東京都福祉局|特別児童扶養手当(国制度)



支給には所得制限があるから、自治体の窓口で確認してね
障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障害により日常生活において常時介護が必要な子どもを養育している家庭に支給される手当。
支給額(令和5年度):月額15,690円
参考|東京都福祉局|障害児福祉手当(国制度)



こちらも所得制限があるから、条件を満たしているか確認してね
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
ひとり親家庭の生活や自立を支援するため、教育費や生活費、転居費用などの貸付を行う制度。
貸付対象:修学資金、生活資金、転宅資金、技能習得資金など
貸付条件:連帯保証人がいれば無利子、いなければ年1%の利息が発生



無利子もしくは年1%の利息はありがたいよね♪
自立支援教育訓練給付金
親が新たな技能を習得し、就業機会を増やすための教育訓練を助成する制度。
この給付金と次の高等職業訓練促進給付金については、この記事に詳しく書いているよ!
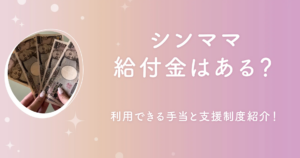
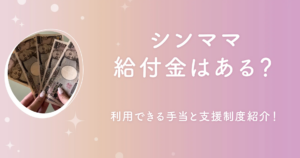
高等職業訓練促進給付金
看護師や保育士など、就職に有利な資格を取得するための訓練期間中の生活費を支援する制度。



この神制度も継続が決定したよ!
シンママなら最大193万円受け取れるシンママ給付金(自立支援教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金)。
活用するなら、インターネット・アカデミーのMamaEduプロジェクトをチェック!
Webデザインやプログラミングなど、在宅での就業が可能なスキルを学べるコースを提供してるよ♪



シンママさんは特に、在宅で働きたい人多いよね
子育てしながら、柔軟なスケジュールで学べるのも魅力だよ。
修了後の就職サポートも充実♪
給付金の予算は自治体ごとに決まってるから、急いで!
奨学金制度
ひとり親家庭の子どもが利用できる奨学金には、給付型奨学金と貸与型奨学金があるよ。
給付型奨学金:経済的に困難な学生を支援する返済不要の奨学金
貸与型奨学金:卒業後に返済が必要な
奨学金



JASSOや地方自治体、民間団体が提供する奨学金制度など多数!
控除や手当を最大限活用しよう
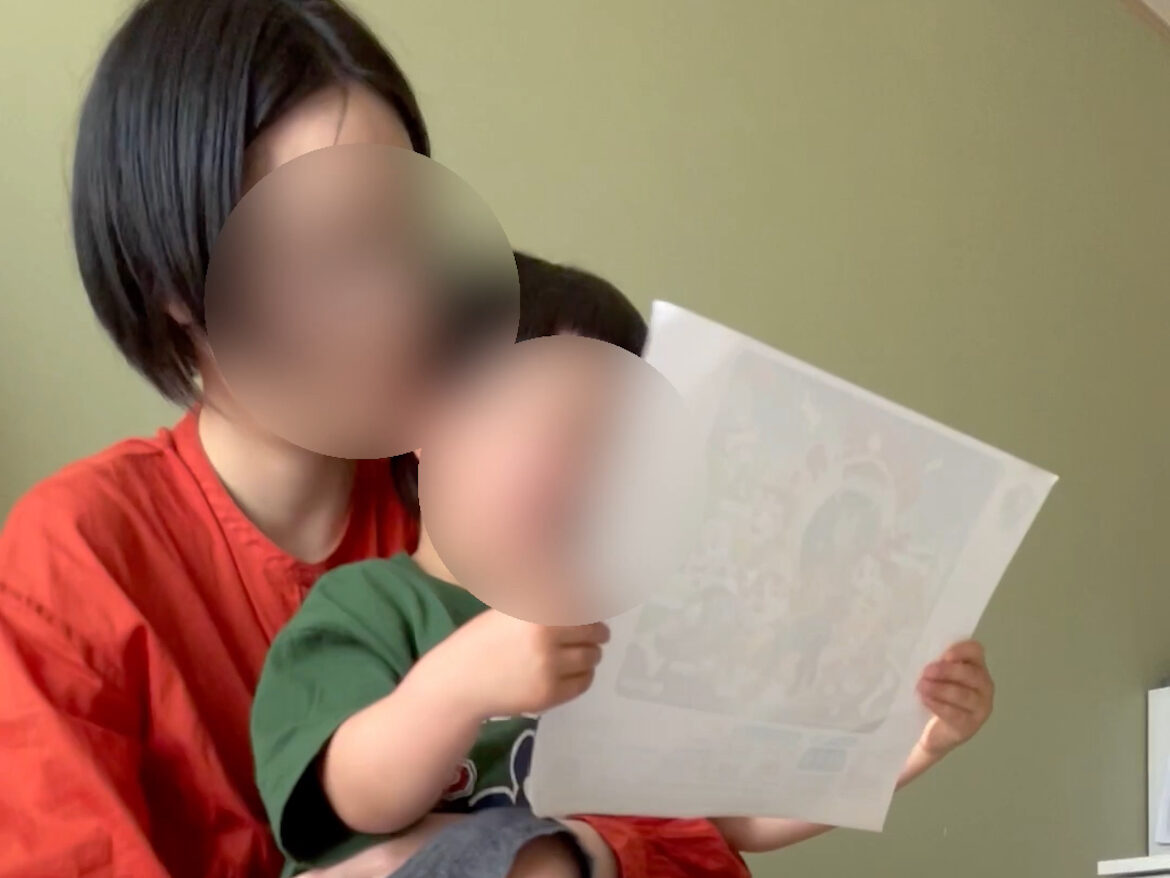
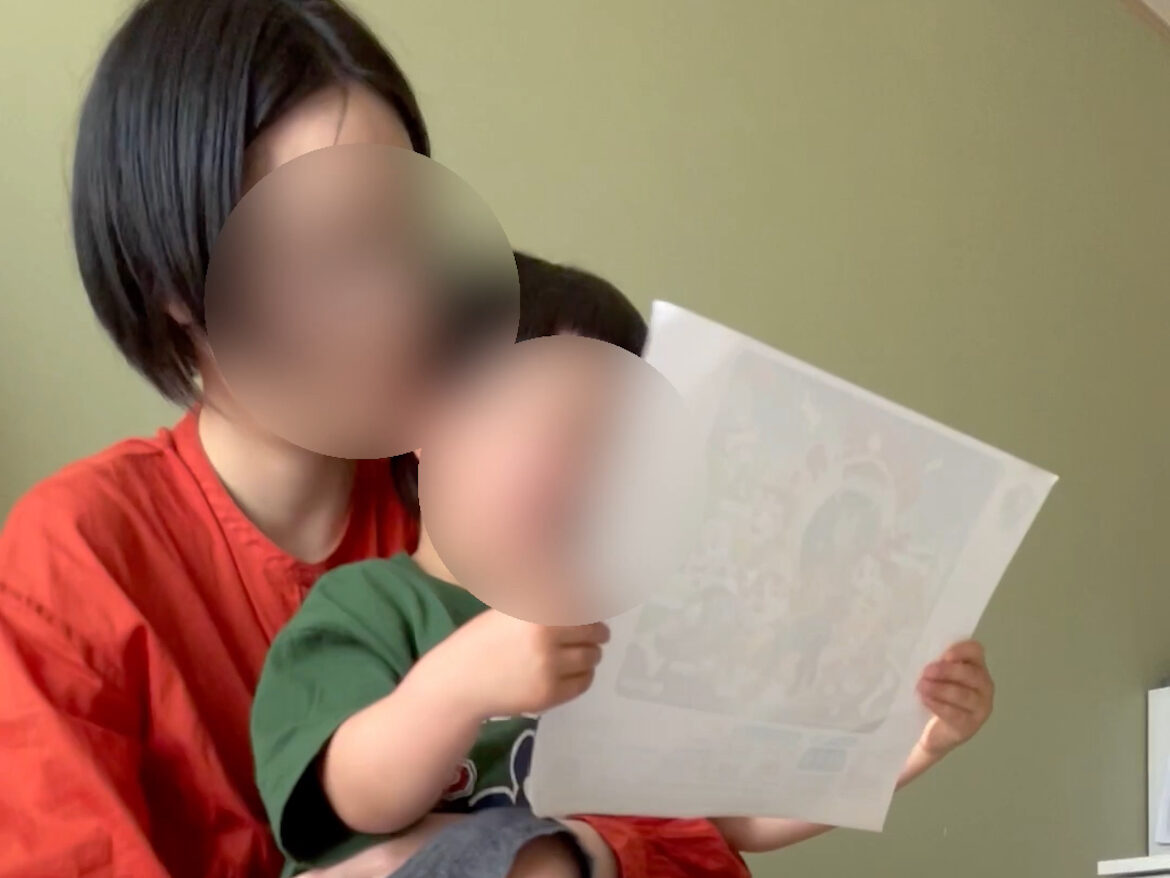
今回は、ひとり親が受けられる控除を紹介したよ。
それぞれの控除の違い、知ってもらえたかな?



ひとり親控除の対象にならなくても、ほかの控除が適用できるかも!
受けられる手当も、自治体によっていろいろあるよ。
所得制限が変わることもあるから、数年前に確認した人はもう1回調べてみるのがおすすめ◎
シンママさんの中には、経済的不安や将来設計を抱えている人が多いんじゃないかな。



かっぴも離婚当時はお金の不安で頭がいっぱいだったよ
保険のぜんぶさんなら、FP(ファイナンシャルプランナー)さんに気軽に相談できちゃうよ♪
初回相談は無料なので、気軽にはじめられて安心!
しかも面談するとプレゼントももらえちゃう。



かっぴはお米もらったよ♪
お金の不安を解消する一歩を踏み出そう◎

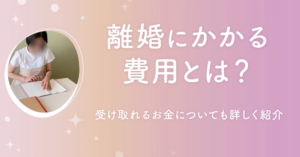

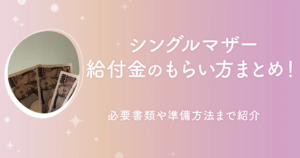
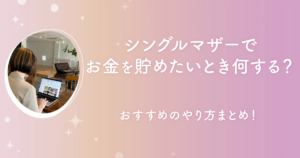

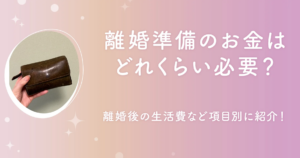
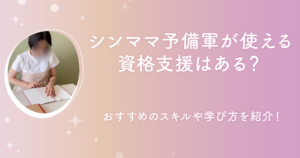
コメント